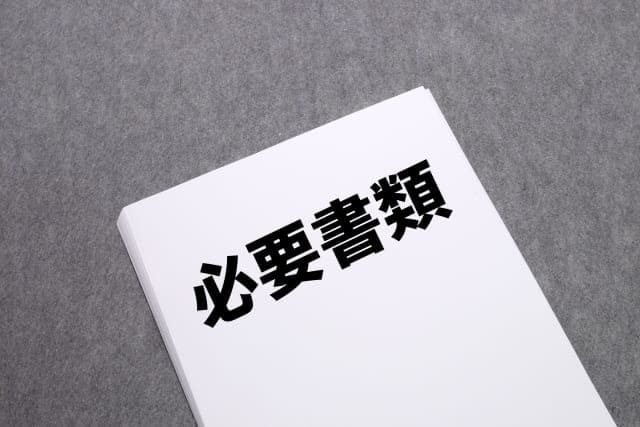blog
共有不動産|持分売却の現実と失敗しないために

- Blog
「父が亡くなって兄弟で実家を相続したけど、自分の持分だけ売れないかな?」
こんな悩みを抱えている方、実は少なくありません。 相続や離婚などで不動産を複数人で共有することになったとき、自分の持分だけを売却したいと考えるのは自然なことです。
でも、実際に持分だけを売却しようとすると、「法的には可能だけど、現実は厳しい」というのが持分売却の実情なのです。
今回は、長崎県大村市で不動産売買の仲介を行っている私たちが、共有不動産の持分売却について、現実的な視点から解説します。
目次
共有不動産の持分とは?基本的な仕組みを理解しよう
共有不動産について正しく理解するために、まずは基本的な仕組みから確認していきましょう。
持分の定義と登記での表記方法
持分とは、一つの不動産を複数人で所有する際の、各共有者の所有権の割合のことです。
例えば、3,000万円の実家を兄弟3人で相続した場合、それぞれが1/3ずつの持分を持つことになります。 この持分は法務局の登記簿に正式に記録され、法律によってしっかりと保護されています。(民法・不動産登記法)
登記簿には「甲区(所有権に関する事項)」の欄に、次のような形で記載されます:
- 田中太郎 持分3分の1
- 田中次郎 持分3分の1
- 田中三郎 持分3分の1
共有名義不動産でできること・できないこと
共有名義の不動産では、持分に応じて権利は保護されますが、実際の利用制限の例を挙げると:
単独でできること
- 自分の持分を売却する
- 自分の持分に抵当権を設定する
- 不動産の現状を維持する行為
全員または過半数の同意が必要なこと
- 建物の解体や建て替え
- 不動産全体の売却
- 第三者への賃貸
つまり、持分を持っていても、その不動産を自由に活用できるわけではないのです。
持分だけの売却は法的に可能?でも現実は厳しい理由
法律上の権利と現実の市場では、大きなギャップがあります。
法的には売却可能だが買い手探しが困難
結論から申し上げると、自分の持分だけを売却することは法的に可能です。(民法)
民法では、共有者は他の共有者の同意を得ることなく、自分の持分を自由に処分できると定められています。
しかし、「法的に可能」と「実際に売れる」は全く別の話です。
一般的な不動産購入者の立場に立って考えてみてください。
持分だけを購入しても、その不動産を自分の思い通りに使えないのです。
リフォームしたくても、賃貸に出したくても、他の共有者の同意が必要になります。
持分売却の現実的な課題
持分売却が困難な理由は、主に以下の3つです:
活用の自由度が低い
持分を購入しても、実際にその不動産を自由に使うことはできません。
住むことも、貸すことも、改修することも、すべて他の共有者の同意が必要です。
将来的なトラブルリスク
見知らぬ第三者が共有者になることで、既存の共有者との間でトラブルが発生する可能性があります。
投資としての魅力が低い
不動産投資として考えた場合、制約が多すぎて収益性が見込めません。
このような理由から、一般の個人が持分だけを積極的に購入することは、ほとんどないのが現実です。
持分売却が困難な3つの理由と市場の現実
持分売却の困難さを、もう少し詳しく見ていきましょう。
買い手が限定的で売却価格が大幅に下がる
持分のみの売却では、売却価格が不動産全体の価値に比べて著しく低くなる傾向があります。
例えば、3,000万円の価値がある不動産の1/3の持分を売却する場合、理論上は1,000万円の価値があります。
しかし、実際の売却価格は300万円~500万円程度になることも珍しくありません。
これは、購入者にとってのリスクと制約が価格に反映されるためです。
共有者間の関係悪化リスク
新たな共有者が加わることで、既存の共有者との関係が悪化する可能性があります。
よくあるトラブル例
- 不動産の管理方針を巡る対立
- 将来の売却時期や価格での意見の相違
- 共有者間のコミュニケーション不足
特に、持分を専門的に買い取る業者が新しい共有者になった場合、その業者が積極的に不動産全体の売却を提案してくることがあります。
これにより、他の共有者が想定していないタイミングで売却の話が持ち上がり、トラブルに発展するケースもあります。
手続きの複雑さと費用負担
持分売却には、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要になる場合があります。
必要な手続き
- 登記手続き(持分移転登記)
- 税務申告(譲渡所得税)
- 共有者への通知
これらの手続きには、それぞれ費用がかかります。
売却価格が低い場合、手続き費用を差し引くと、手元に残る金額がさらに少なくなってしまいます。
持分売却の現実的な選択肢4パターン
それでは、持分を売却したい場合の現実的な選択肢を見ていきましょう。
共有者全員で話し合って不動産全体を売却
最も利益が期待できる方法は、共有者全員で話し合いをして、不動産全体を売却することです。
メリット
- 市場価格での売却が可能で、最も高い売却価格が期待できる
- 持分割合に応じて売却代金を分配するため公平性が保たれる
- 共有関係を完全に解消できる
- 手続きが明確で、トラブルのリスクが最も少ない
進め方のポイント
- 共有者全員で売却の意向を確認する
- 不動産の査定を取得し、売却価格の目安を把握する
- 売却時期や条件について話し合う
- 信頼できる不動産会社に仲介を依頼する
- 売却代金を持分割合に応じて分配する
例えば、3,000万円で売却できた場合、1/3の持分を持つ方は1,000万円を受け取ることができます。
これは他の方法と比較して、有利な条件です。
ただし、共有者全員の合意が必要なため、一人でも反対する方がいる場合は、この方法を選択することはできません。
他の共有者への売却交渉
最も円満な解決方法は、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうことです。
メリット
- 第三者に売却するよりも手続きが簡単
- トラブルのリスクが少ない
進め方のポイント
- まずは他の共有者に状況を説明し、売却の意向を伝える
- 不動産全体の査定を取得し、適正な持分価格を算出する
- 支払い方法(一括・分割)について相談する
- 必要に応じて、不動産の専門家に間に入ってもらう
感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが成功の鍵です。
売却したい理由や今後の希望を、丁寧に説明しましょう。
専門買取業者への売却
他の共有者が買い取れない場合は、共有持分の買取を専門とする業者への売却を検討することになります。
特徴
- 一般の個人では買い手がつかない持分を買い取ってくれる
- 手続きがスムーズで、比較的短期間で売却できる
- 買取後は、業者が他の共有者と交渉を行う
注意点
- 売却価格が相場より大幅に安くなる
- 買取業者によって提示価格に差がある
- 業者の信頼性を事前に確認する必要がある
持分放棄という選択肢
売却ではなく、持分を放棄して他の共有者に無償で譲渡する方法もあります。
メリット
- 共有関係から完全に抜け出せる
- 売却価格を気にする必要がない
- 手続きが比較的簡単
デメリット
- 放棄を受ける側に贈与税が発生する可能性(国税庁情報)
- 登記費用などの実費は発生する
- 一度放棄すると取り消せない
持分放棄を検討する場合は、事前に税理士に相談して、税金面での影響を確認することが重要です。
共有不動産トラブルを避けるための注意点とデメリット
持分売却を成功させるためには、事前の準備と注意深い進め方が欠かせません。
事前準備で失敗を防ぐ
他の共有者との十分な話し合い まずは、他の共有者と十分に話し合うことが最も重要です。
- 売却したい理由を明確に伝える
- 相手の状況や意向も理解する
- 可能な限り、全員が納得できる解決策を模索する
感情的な対立を避け、建設的な話し合いを心がけましょう。
専門家のサポートを活用 共有不動産の問題は複雑で、法的な知識も必要になります。
必要に応じて、以下の専門家に相談することをお勧めします:
- 不動産会社(査定・売却サポート)
- 税理士(税金関係)
- 司法書士(登記手続き)
- 弁護士(法的トラブル)
税金と費用の確認を怠らない
持分の売却や放棄には、様々な税金や費用が発生します。
主な税金
- 譲渡所得税(売却益に対して)
- 贈与税(持分放棄の場合)
- 登録免許税(登記手続き)
主な費用
- 司法書士報酬
- 仲介手数料
- 各種書類取得費用
事前に専門家に相談し、正確な費用を把握しておくことで、予期せぬ出費を避けることができます。
よくある質問:共有持分売却の疑問を解決
Q1. 持分売却に他の共有者の同意は必要ですか?
A1. 法的には同意は不要ですが、実際には事前に相談することをお勧めします。
民法上、共有者は自分の持分を自由に処分できるとされています。
しかし、事前に他の共有者に相談することで、トラブルを避け、より良い解決策が見つかる可能性があります。
Q2. 持分売却の相場はどのくらいですか?
A2. 不動産の価値の30%~50%程度が一般的です。
ただし、立地条件や不動産の種類、共有者の状況によって大きく変わります。
正確な価格を知るためには、不動産の専門家による査定が必要です。
Q3. 持分売却後の税金はどうなりますか?
A3. 売却益が出た場合は譲渡所得税がかかります。(国税庁情報)
売却価格から取得費と売却にかかった費用を差し引いた金額が売却益となり、この金額に対して税金がかかります。
具体的な税額は、所有期間や売却価格によって変わるため、税理士に相談することをお勧めします。
Q4. 持分だけでも住宅ローンは組めますか?
A4. 困難です。
持分のみを担保とした住宅ローンは、金融機関にとってリスクが高いため、ほとんどの場合で融資を受けることはできません。
現金での購入が前提となることが多いです。
まとめ:共有不動産問題は専門家と一緒に解決しよう
共有不動産の持分売却は、法的には可能ですが、現実的には多くの困難が伴います。
重要なポイントをまとめると:
- 他の共有者との話し合いが最も重要で、まずは円満な解決を目指しましょう
- 持分のみの売却は価格が大幅に下がることを理解しておきましょう
- 専門家のサポートを活用して、最適な解決方法を見つけましょう
- 税金や費用の確認を怠らず、事前に正確な情報を収集しましょう
共有不動産の問題は、当事者だけで解決しようとすると、思わぬトラブルに発展することがあります。
不動産の専門家や法的な専門家と連携しながら、段階的に解決していくことが成功への近道です。
私たち株式会社あこう不動産では、お客様の不動産問題の解決をサポートしています。
相続や共有不動産でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
一人で悩まず、専門家と一緒に最適な解決策を見つけていきましょう。
まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。
▼無料相談のお申し込みはこちらから
不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。