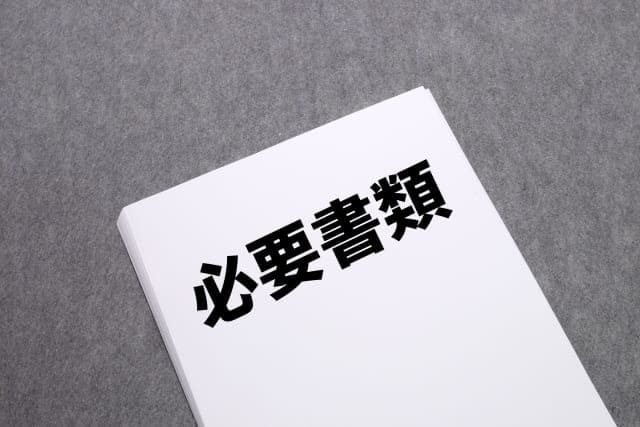
「書類がない」で査定額が下がる?不動産売却前に揃えておくべき必要書類
初めて不動産の売却を考えたとき、「まずは査定を依頼しよう」と思われる方は多いでしょう。
でも、いざ査定の連絡をしたら「いくつか書類を用意してください」と言われて、「え、何を準備すればいいの?」と戸惑ってしまう可能性があります。
実は、不動産査定では書類の有無が査定額に影響することがあります。
必要な書類が揃っていないと、正確な価値が伝わらず、本来の価格よりも低い査定額を提示されてしまうこともあるのです。
この記事では、不動産売却を検討されている方に向けて、査定の際に準備しておくべき書類と、書類がない場合のリスクや対処法を解説します。
不動産査定で書類が重要な理由
不動産会社が査定を行う際、物件の価値を正確に判断するためには「客観的な情報」が必要です。
書類は、その物件がどのような状態で、どのような権利関係にあるのかを証明する証拠になります。
たとえば、権利証があれば所有者であることが明確になりますし、固定資産税納税通知書があれば土地や建物の固定資産税評価額がわかります。
建築確認済証・検査済証があれば、建物が法令に適合して建てられたことが証明できます。
これらの書類がないと、不動産会社は慎重な(=低めの)査定額になりがちです。
また、売却活動に進んだ際にも、書類が揃っていないと買主の住宅ローンの審査に通りにくくなるケースもあります。
つまり、書類の準備は査定の精度を上げるだけでなく、スムーズな売却を実現するための第一歩なのです。
査定方法によって必要な書類は変わる?机上査定と訪問査定の違い
不動産査定には、大きく分けて「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定(詳細査定)」の2種類があります。
机上査定は、物件の住所や面積、築年数などの基本情報をもとに、過去の取引事例や市場相場から概算の査定額を算出する方法です。
現地を見ずに行うため、短時間で結果が出るのが特徴ですが、精度はやや低めです。
この段階では、厳密に書類を揃える必要はありません。
一方、訪問査定は、実際に不動産会社の担当者が現地を訪れて、建物の状態や周辺環境、日当たり、近隣との境界などを詳しく確認する方法です。
この段階では、物件の細かな情報が必要になるため、書類が揃っているほど正確な査定額が算出されます。
また、訪問査定の結果は売却活動の基礎資料にもなるため、できるだけ多くの書類を準備しておくことが望ましいです。
机上査定では概算を知り、訪問査定で正確な価格を把握するという流れが一般的ですので、訪問査定の際には書類をしっかり揃えておきましょう。
【不動産査定の種類とは】
不動産査定に必要な書類一覧
ここからは、具体的にどのような書類が必要なのかを見ていきましょう。
書類は大きく分けて、「必ず準備したい基本書類」と「あれば査定精度が高まるプラス書類」の2つに分けられます。
必ず準備したい基本書類
まずは、査定の際に必須となる基本的な書類をご紹介します。
・登記済証または登記識別情報(権利証)
物件の所有者であることを証明する最も重要な書類です。
法務局から発行されるもので、不動産を取得した際に受け取っているはずです。
これがないと売却はできますが、引き渡し時に費用が発生します。
・建物図面
建物の配置や各階の間取りを示す図面で、建物の構造を理解するために使われます。
手元にある場合は準備しておくと、査定がスムーズに進みます。
・固定資産税納税通知書
毎年春頃に市区町村から送られてくる書類で、土地や建物の評価額や税額が記載されています。
この書類があれば、物件の公的な評価額を正確に把握でき、維持費の計算にも役立ちます。
手元にない場合は、不動産会社が委任状をもとに公課証明書として取得することも可能です。
・土地測量図・地積測量図
土地の面積や形状、境界を示す図面です。
法務局で取得でき、土地の正確な広さを証明するために必要です。
こちらも不動産会社が代わりに取得できる書類ですが、手元にあればすぐに確認できます。
これらの基本書類は、物件の権利と状態を明確にするための土台となるものです。
査定精度を高めるプラス書類
次に、必須ではないものの、あることで査定額が上がったり、売却がスムーズになる書類をご紹介します。
・建築確認済証・検査済証
建物が建築基準法に適合して建てられたことを証明する書類です(建築基準法)。
この書類がないと買主が住宅ローンの審査が通りにくくなることがあり、売却時の査定額に影響するケースがあります。
・建築設計図書・パンフレット
建物の構造や使用されている断熱材、設備の仕様などが詳しく記載されています。
これがあると、建物の品質を正確に伝えることができます。
・境界確認書(筆界確認書)
隣地との境界が確定していることを示す書類です。
土地の売却では、境界が不明確だとトラブルの原因になるため、この書類の有無は非常に重要です。
・リフォーム・メンテナンスの履歴
屋根や外壁の塗装、内装のリフォーム、シロアリ駆除などの記録です。
適切な管理がされていることを証明でき、プラス評価につながります。
これらの書類は、物件の価値をより正確に、そして高く評価してもらうための武器になります。
【不動産査定価格は交渉できる?】
書類を紛失している場合の対処法
「書類が見つからない」「そもそも受け取った記憶がない」という方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、書類を紛失している場合の対処法をご紹介します。
再取得できる書類・できない書類
まず知っておきたいのは、書類によっては再取得が可能なものと、できないものがあるという点です。
再取得が可能な書類としては、登記簿謄本(登記事項証明書)、土地測量図、固定資産税評価証明書などがあります。
これらは法務局や市区町村の役所で取得できます。
一方、権利証(登記済証・登記識別情報)は再発行できません。
紛失した場合は、司法書士に依頼して「本人確認情報」という書類を作成してもらう必要があります。
費用は数万円程度かかりますが、この手続きを行えば売却を進められます。
また、建築確認済証や検査済証も原則として再発行されませんが、役所で「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」を取得することで、一定の証明はできます。
紛失している書類がある場合は、まず不動産会社に相談して、どの書類が必須で、どう対処すればよいかを確認するのが最善です。
【不動産査定トラブルを避けるための方法】
法務局や市役所での取得方法
書類の取得は、それぞれの管轄機関で行います。
登記簿謄本や測量図、建物図面は法務局で取得できます。
窓口での申請のほか、オンラインでの請求も可能で、登記情報提供サービスを利用すれば自宅にいながらPDFで取得できます(手数料は1通数百円程度)。
固定資産税評価証明書や公課証明書は市区町村の役所で取得できます。
窓口に本人確認書類を持参、または不動産会社へ委任すれば、当日中に発行してもらえます。
建築計画概要書や台帳記載事項証明書も市区町村の建築指導課などで取得可能です。
物件の所在地と地番がわかれば、誰でも取得できる書類もありますので、不動産会社と相談して揃えていきましょう。
書類の取得には時間がかかることもあるため、早めに動き始めることが大切です。
よくある質問
Q. 査定を依頼する前に全ての書類を揃える必要がありますか?
A. すべて揃っている必要はありませんが、基本的な書類は手元にあると安心です。
もし手元にない書類があっても、まずは不動産会社に相談してみましょう。
査定を進めながら、必要な書類を段階的に揃えていくことも可能です。
Q. 相続した不動産を査定する場合、特別な書類は必要ですか?
A. 相続登記が完了していない不動産の場合、通常の書類に加えて相続関係を証明する書類が必要になることがあります。
具体的には、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などです。
相続登記が済んでいない場合は、登記簿上の名義が亡くなった方のままになっているため、売却までに相続登記を行う必要があります(民法に基づく相続手続き)。
令和6年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料が科される可能性もあるため、早めの対応をおすすめします。
【相続不動産売却の税金の特例について】
Q. 古い物件で図面や書類が一切残っていない場合はどうすればいいですか?
A. 書類がなくても売却は可能ですが、査定額や売却のスムーズさに影響するため、できる範囲で情報を集めることが大切です。
古い物件では、建築当時の書類が残っていないケースも珍しくありません。
その場合でも、売却ができないわけではありませんので、まずは不動産会社へ相談してみましょう。
まとめ:早めの書類準備が安心な売却への第一歩
不動産査定において、書類の準備は単なる「手続き」ではなく、物件の価値を正確に伝え、適正な査定額を得るための重要なステップです。
権利証や固定資産税納税通知書などの基本書類はもちろん、建築確認済証や境界確認書、リフォーム履歴などがあれば、査定の精度が高まり、売却もスムーズに進みます。
書類が見つからない場合でも、法務局や市区町村で再取得できるものは多くあります。
まずは手元にある書類を確認し、足りないものがあれば早めに対処しましょう。
不動産の売却は人生の中でも大きな決断です。
後悔のない売却を実現するために、書類の準備から丁寧に進めていきましょう。
まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。
▼無料相談のお申し込みはこちらから
[無料査定を依頼する]
[不動産について相談する]
[LINEで相談する]
不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。









