blog
相続した土地が負担に…国に引き取ってもらえる制度があるって本当?
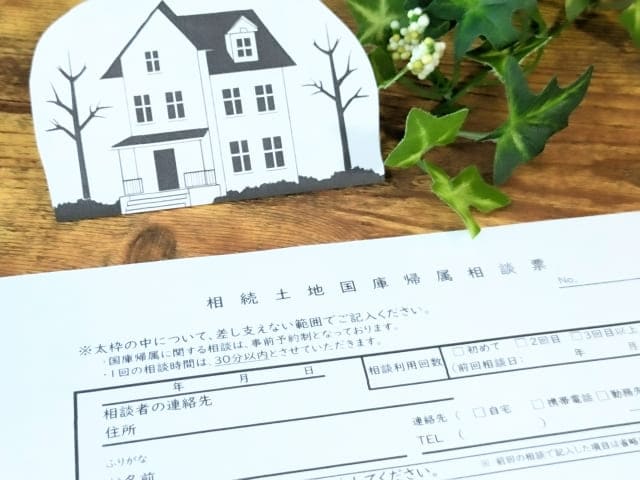
- Blog
「親から相続した土地、正直なところ管理が大変で…」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか
使い道のない土地でも固定資産税は毎年かかりますし、草刈りや管理も必要です。
売却しようにも買い手が見つからない、かといって放置するわけにもいかない。
そんな悩みを抱える土地所有者のために、2023年に新しい制度がスタートしました。
「相続土地国庫帰属制度」という、相続した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。(法務省)
目次
相続した土地の管理でお困りではないでしょうか
現在の日本では、相続した土地の処分に関する深刻な問題が広がっています。
所有者不明土地が増え続ける現状
少子高齢化と過疎化の進行により、全国で管理されない土地が急増しています。
国土交通省の調査によると、所有者不明の土地は九州本島に匹敵する面積にまで拡大しているのが現状です。
相続が発生しても登記手続きを行わないケースや、相続人が土地の存在すら把握していないケースも珍しくありません。
このような土地は適切な管理が行われず、周辺環境への悪影響や公共事業の阻害要因となることもあります。
固定資産税や管理責任の重い負担
相続した土地には、利用の有無に関わらず様々な負担が伴います。
毎年の固定資産税はもちろん、草刈りや清掃といった管理業務も所有者の責任です。
特に遠方にある土地の場合、管理のために交通費や宿泊費がかかることも珍しくありません。
土地を所有し続けることで発生するコストは、想像以上に大きな負担となってしまいます。
相続土地国庫帰属制度とは何か?基本的な仕組みを解説
相続によって取得した土地の負担軽減を目的とした制度についてご説明します。
制度創設の背景と目的
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された比較的新しい制度です。(法務省)
所有者不明土地の発生予防と、相続人の負担軽減を主な目的として創設されました。
制度の利用により、土地の管理責任や固定資産税などの負担から解放される可能性があります。
国に土地を引き取ってもらうメリット
制度を活用することで得られる主なメリットをご紹介します。
- 固定資産税の負担からの解放:土地の所有権を手放すことで、毎年の税負担がなくなります
- 管理責任の免除:草刈りや清掃などの維持管理業務が不要になります
- 将来への安心:次世代に負の遺産を残さずに済みます
- 精神的負担の軽減:土地に関する悩みやストレスから解放されます
ただし、誰でも簡単に利用できる制度ではなく、厳格な要件を満たす必要があることも事実です。
制度の利用を検討する際は、メリットだけでなくデメリットや制約についても十分理解することが重要です。
国が受け入れる土地の条件|対象となる土地・対象外の土地
国庫帰属制度を利用するためには、厳しい条件をクリアする必要があります。
建物や担保権の有無による判定基準
制度を利用できない土地の代表的な例をご紹介します。
建物が残存している土地は、原則として引き取り対象外となります。
住宅や倉庫、工作物などが残っている場合、申請前に解体・撤去を完了させる必要があります。
担保権が設定されている土地も対象外です。
住宅ローンの抵当権や、地上権、賃借権などが登記されている土地は、これらの権利を抹消してからでないと申請できません。
また、他人の利用に供されている土地(通路として使用されている土地や墓地など)も引き取ってもらえません。
境界確定や土壌汚染など重要なチェックポイント
土地の物理的・法的な状況についても厳格な審査が行われます。
隣地との境界が不明確な土地は対象外となります。
境界標の設置や隣地所有者との境界確認書の取り交わしなど、所有範囲を明確にする作業が必要です。
土壌汚染や地下埋設物がある土地も引き取り対象から除外されます。
過去に工場や給油所として利用されていた土地、産業廃棄物が埋設されている可能性がある土地などは、事前の調査と対策が求められます。
さらに、崖崩れなどの災害リスクが高い土地も対象外となる場合があります。
管理コストが高い土地が除外される理由
国が引き取る土地は、将来にわたって適切な管理が可能である必要があります。
管理に多額の費用や特別な技術を要する土地は、原則として対象外です。
また、定期的な設備点検や専門的な維持管理が必要な土地も除外対象となります。
国としても税収で管理していく以上、過度な負担となる土地の受け入れは困難というのが実情です。
申請手続きの流れと必要な準備|法務局での手続き方法
実際に制度を利用する場合の具体的な手続きについて解説します。
事前相談から承認までのステップ
制度利用の第一歩は、管轄法務局での事前相談です。
ステップ1:事前相談 土地の所在地を管轄する法務局に相談し、制度の対象となり得るかを確認します。 この段階で基本的な要件チェックが行われます。
ステップ2:申請手続き 必要書類を揃えて正式な申請を行います。 申請時には審査手数料(土地1筆あたり14,000円)の納付が必要です。
ステップ3:書類審査と現地調査 法務局による詳細な審査が実施されます。 書面審査に加えて、実際に現地での調査も行われます。
ステップ4:承認通知と負担金納付 審査を通過すると、法務大臣からの承認通知が届きます。 その後、定められた負担金を納付することで手続きが完了します。
必要書類と現地調査の内容
申請には多数の書類が必要となります。
主な必要書類
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 公図・地積測量図
- 境界確認に関する書類
- 相続関係を証明する戸籍謄本等
- 固定資産税納税証明書
現地調査では以下の項目が確認されます
- 土地の現況と登記内容の一致
- 境界の明確性
- 周辺への影響の有無
- 管理上の問題点の確認
申請前に整備しておくべき事項
建物等の撤去:残存する建物や工作物がある場合は、申請前に解体を完了させておきましょう。
境界の確定:隣地所有者との境界確認や測量を実施し、境界標の設置を行います。
権利関係の整理:抵当権等の担保権がある場合は、事前に抹消登記を済ませておく必要があります。
相続関係の証明:相続登記が未了の場合でも申請は可能ですが、相続関係を証明する戸籍謄本等の書類を整備しておきます。
事前準備を怠ると申請が却下される可能性が高くなるため、十分な準備期間を確保することが大切です。
気になる費用負担|負担金の算定方法と支払い時期
制度を利用する際に必要な費用について解説します。
宅地・農地・森林別の負担金額
負担金は土地の種類と立地条件によって算定方法が異なります。
代表的な負担金の例
- 一般的な宅地:20万円(郊外の住宅地など)
- 市街地の宅地:面積に応じ算定
- 農地:20万円(市街地や農用地区域などは面積に応じ算定)
- 森林:面積に応じ算定
- その他の土地(雑種地・原野等):20万円
より詳細な条件や計算方法については、法務省の公式サイトをご確認ください。
土地の所在地や用途地域の指定状況により算定方法が変わるため、事前に管轄の法務局に相談されることをお勧めします。
10年分の管理費用相当額の考え方
負担金の算定基準は、国が土地を管理するために要する10年分の費用相当額とされています。
この考え方は、土地を国に引き渡した後の管理コストを申請者が負担するという制度設計に基づいています。
宅地の場合の20万円という金額は、年間2万円の管理費用を想定した計算です。
ただし、特殊な管理が必要な土地については、標準的な金額を上回る負担金が設定される可能性もあります。
負担金の支払いは承認通知後となるため、申請時点では審査手数料のみの負担で済みます。
制度利用前に知っておきたい注意点とデメリット
制度には多くのメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。
申請却下のリスクと手数料について
制度の要件は非常に厳格で、申請が却下されるケースも少なくありません。
却下される主な理由
- 建物の解体が不完全
- 境界が不明確
- 土壌汚染の可能性
- 管理コストが過大
重要なのは、申請が却下されても審査手数料(14,000円)は返還されないということです。
事前相談を十分に行い、要件を満たしていることを確認しておきましょう。
共有名義の土地で必要な全員同意
相続により複数人で共有している土地の場合、特別な注意が必要です。
共有者全員の同意がなければ申請できません。
一人でも反対者がいる場合、制度の利用は不可能となります。
共有者間での話し合いや合意形成に時間がかかる場合も多く、手続きが長期化する可能性があります。
想定される申請から完了までの期間
制度利用には相応の時間を要することを理解しておきましょう。
事前相談から申請、審査、承認まで含めると、半年から1年程度の期間が必要と考えられます。
特に現地調査や書類の補正が必要な場合は、さらに期間が延びる可能性があります。
急いで土地を手放したい場合には、この制度は必ずしも適さない場合があることも考慮しておく必要があります。
よくある質問|相続土地国庫帰属制度のQ&A
建物解体費用は誰が負担するのか?
建物の解体費用は、申請者(土地所有者)の負担となります。
国は更地の状態でしか土地を引き取らないため、申請前に所有者自身で解体を完了させる必要があります。
解体費用と負担金を合計した総額で、制度利用の是非を判断することが重要です。
他の処分方法との比較検討ポイント
国庫帰属制度以外の選択肢も検討することが大切です。
売却の検討:市場価値がある土地の場合、売却により費用負担なく手放せる可能性があります。
寄付の検討:地方自治体や法人への寄付という選択肢もありますが、受け入れ条件は厳しいのが実情です。
管理委託:土地を手放さずに管理を専門業者に委託する方法もあります。
各選択肢のメリット・デメリットを比較検討し、最適な方法を選択することが重要です。
まとめ|相続土地の処分は専門家への相談が重要
相続土地国庫帰属制度について、解説してまいりました。
制度活用の判断基準
制度を利用すべきかどうかの判断基準をまとめると、以下のようになります。
制度利用が適している場合
- 売却の見込みが全くない土地
- 管理負担が重く、今後も利用予定がない土地
- 相続人全員が手放すことに同意している場合
- 必要な費用(解体費用+負担金)を負担できる場合
慎重な検討が必要な場合
- 将来的に売却の可能性がある土地
- 解体費用等の負担が困難な場合
- 共有者間で意見が分かれている場合
売却や寄付も含めた総合的な検討の必要性
相続土地国庫帰属制度は、土地を手放す選択肢の一つに過ぎません。
まずは売却の可能性を検討し、それが困難な場合の選択肢として制度利用を考えることをお勧めします。
また、制度の要件は厳格で、準備には相応の時間と費用がかかることも考慮が必要です。
相続土地の処分でお困りの際は、まず不動産の専門家に相談されることをお勧めします。
当社では、相続不動産に関する豊富な経験を活かし、お客様にとって最適な解決方法をご提案いたします。
土地の査定から各種手続きのサポートまで、安心してお任せください。
お困りの土地がございましたら、お気軽にご相談ください。
無料相談は下記からお申し込みいただけます。
▼無料相談のお申し込みはこちらから
不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。







