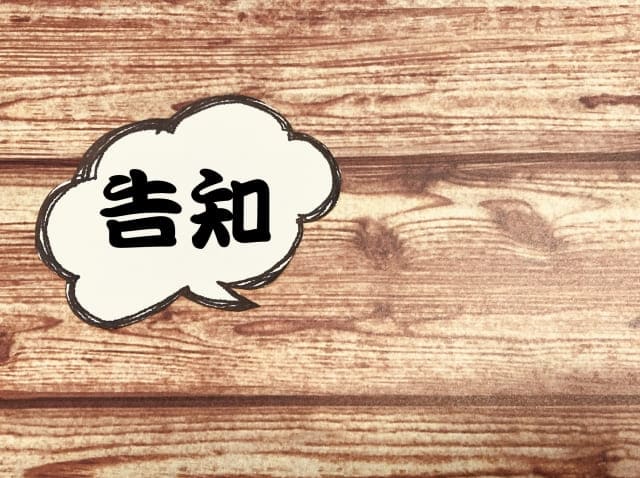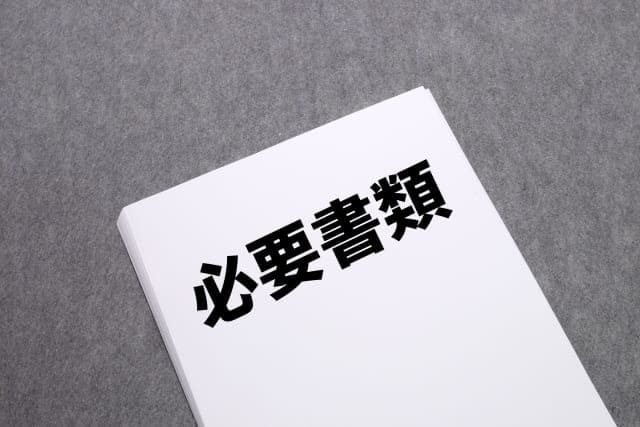blog
不動産売却時の固定資産税は誰が払う?日割り精算の計算方法と注意点を解説
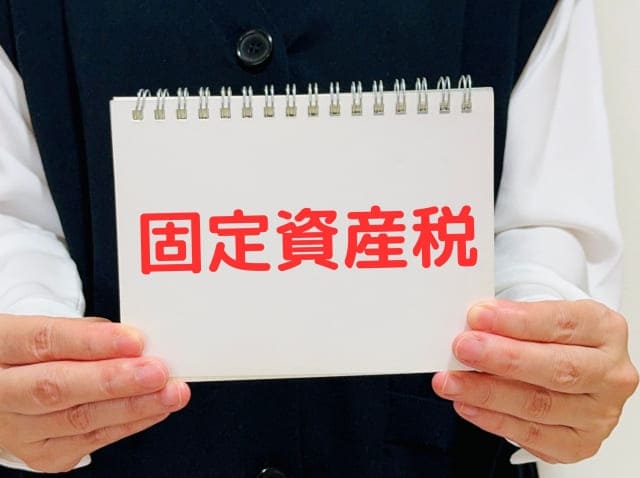
- Blog
「固定資産税って、売った後はどうなるんだろう?」
「年の途中で売ったら、税金は誰が払うの?」
実は私も、不動産業界に入る前は「売ったら買主が払うんだろう」と漠然と思っていました。
ところが、実際には少し複雑な仕組みになっています。
この記事では、不動産売却時の固定資産税について、納税義務者は誰なのか、日割り精算とは何か、そして計算方法や注意点まで、初めて不動産を売却する方にもわかりやすく解説していきます。
目次
不動産を売却したら固定資産税は誰が負担するの?
不動産売却を検討している方から、よくこんな質問をいただきます。
「3月に売却したら、その年の固定資産税は買主が払ってくれるんですよね?」
残念ながら、答えは「いいえ」です。
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人です。
つまり、年の途中で売却したとしても、法律上は売主であるあなたが1年分の固定資産税を納める義務があります。
「えっ、それって不公平じゃない?」
そう思いますよね。
そこで、不動産売買の実務では「日割り精算」という慣習が生まれました。
これから、その仕組みを詳しく見ていきましょう。
固定資産税の納税義務者は「1月1日時点の所有者」
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している登記簿上の名義人に課税される仕組みになっています(地方税法)。
自治体から納税通知書が届くのは、通常4月から6月頃です。
ここで大切なポイントがあります。
年の途中で不動産を売却しても、納税義務者は変わりません。
例えば、2025年8月に不動産を売却したとしましょう。
この場合、2025年1月1日時点では売主であるあなたが所有者でした。
そのため、2025年度の固定資産税は、売主であるあなたが全額納税する義務があります。
買主に名義が移った後でも、その年度の税金の納付書はあなたのところに届き続けます。
自治体は、年の途中で所有者が変わったことを固定資産税の計算には反映しないのです。
このルールを知らずに「売ったから関係ない」と放置してしまうと、未納になってしまいます。
まずはこの基本ルールを押さえておきましょう。
実務では引渡し日を基準に日割り精算するのが一般的
法律上は売主が全額負担と説明しましたが、実際の不動産取引では違う扱いになります。
引渡し日を境に、売主と買主で固定資産税を分担する「日割り精算」が一般的な慣習です。
なぜこのような慣習が生まれたのでしょうか。
理由は簡単です。
売主が所有していない期間の税金まで売主が負担するのは、やはり公平ではないからです。
日割り精算の流れは次のとおりです。
引渡し日より前の期間 → 売主が負担
引渡し日以降の期間 → 買主が負担
そして、買主が負担する分の金額を、決済時に売買代金とは別に売主へ支払います。
注意していただきたいのは、日割り精算は法律上の義務ではなく、あくまで商慣習だということです。
そのため、売買契約書にきちんと記載されていないと、精算されないこともあります。
契約書に「公租公課の精算」や「固定資産税等の日割り精算」という条項があるか、必ず確認しましょう。
固定資産税の日割り計算方法をわかりやすく解説
ここからは、実際にどうやって日割り計算をするのか、具体的に見ていきます。
精算の基準日は「引渡し日」
日割り精算では、引渡し日(決済日)を境界として、売主負担期間と買主負担期間を分けます。
引渡し日当日は、一般的に買主の負担となります。
例えば、2025年6月15日が引渡し日の場合、
- 売主負担:1月1日(または4月1日)から6月14日まで
- 買主負担:6月15日から12月31日(または翌年3月31日)まで
このように分けて計算します。
基本的な計算式
日割り精算の計算式は、次のとおりです。
買主負担額 = 年間固定資産税額 ÷ 年間の日数 × 買主の所有日数
年間の日数は、通常365日ですが、うるう年の場合は366日で計算します。
売主は、年間の固定資産税額から買主負担額を差し引いた金額を実質的に負担することになります。
具体的な計算例
実際に数字を使って計算してみましょう。
【前提条件】
- 年間固定資産税額:12万円
- 引渡し日:2025年9月1日
- 起算日:4月1日(関西方式)
- 2025年は平年(365日)
【計算】
買主の所有日数 = 9月1日〜翌年3月31日 = 212日
買主負担額 = 120,000円 ÷ 365日 × 212日 = 69,698円
売主負担額 = 120,000円 – 69,698円 = 50,302円
つまり、決済時に買主から売主へ不動産の代金とは別に69,698円の精算金が支払われます。
この計算により、売主は実質的に約5万円の負担、買主は約7万円の負担となり、所有期間に応じた公平な分担が実現します。
起算日は関東と関西で違う!地域による精算方法の違い
日割り精算を理解する上で、最も注意が必要なのが「起算日」です。
起算日とは、1年間の始まりをいつとするかという基準日のことです。
実は、この起算日が地域によって異なるため、同じ引渡し日でも精算金額が変わることがあります。
1月1日起算(関東圏に多い)
関東圏では、1月1日を起算日とする慣習が一般的です。
この場合、その年の1月1日から12月31日までを1年間として計算します。
【計算期間】
- 売主負担:1月1日〜引渡し日の前日まで
- 買主負担:引渡し日〜12月31日まで
1月1日起算のメリットは、暦年と一致しているため理解しやすいことです。
4月1日起算(関西圏に多い)
一方、関西圏では、4月1日を起算日とする慣習が主流です。
長崎県大村市も、4月1日を起算日とすることが主流です。
【計算期間】
- 売主負担:4月1日〜引渡し日の前日まで
- 買主負担:引渡し日〜翌年3月31日まで
4月1日起算の場合、年をまたぐ取引では計算がやや複雑になることがあります。
どちらを選ぶべき?
「じゃあ、どっちで計算すればいいの?」
これは、取引する地域の慣習に従うのが基本です。
ただし、最も重要なのは、売買契約書に起算日を明確に記載し、売主・買主双方が合意することです。
「1月1日を起算日として固定資産税等を日割り計算する」
「4月1日を起算日として固定資産税等を日割り計算する」
このように、契約書に明記されていれば、後からトラブルになることはありません。
当社では長崎県大村市を拠点としているため、通常は4月1日起算での精算をご提案しています。
固定資産税精算でトラブルにならないための注意点
日割り精算は一般的な慣習ですが、きちんと対応しないとトラブルの原因になります。
ここでは、失敗しないためのチェックポイントをご紹介します。
起算日は売買契約書に必ず明記する
前の章でも触れましたが、起算日の認識違いは最も多いトラブルです。
売主が「1月1日起算だと思っていた」、買主が「4月1日起算だと思っていた」という食い違いが起これば、精算金額が大きく変わってしまいます。
特に、関東から関西など、県外へ転居のケースでは要注意です。
契約書に「1月1日を起算日とする」または「4月1日を起算日とする」と明記し、不動産会社の担当者にも確認してもらいましょう。
曖昧なまま進めると、決済直前にトラブルになることもあります。
税額確定前は前年度の金額で暫定精算
不動産の引渡し時期によっては、その年の固定資産税額がまだ確定していないことがあります。
このような場合は、前年度の固定資産税額を基準に暫定的に精算する方法が一般的です。
契約書には、「固定資産税等の精算は、引渡し時点で令和◯年度の税額が確定していない場合、令和◯年度の税額をもって計算する」といった条項を入れておきます。
実務上は、固定資産税の金額が大きく変わることは少ないため、前年度の金額での精算で問題になることはほとんどありません。
ただし、建物を解体した場合、大規模な土地開発があった場合、評価替えがあった場合は、税額が大きく変動する可能性があるため注意が必要です。
売却前に未納がないか必ず確認
意外と見落としがちなのが、固定資産税の未納です。
固定資産税が未納のままでは、スムーズに引渡しができない可能性があります。
金融機関によっては、固定資産税の未納があると融資を実行しないケースもあります。
売却を決めたら、未納分がないかチェックしましょう。
もし未納がある場合は、売却前に必ず完納しておくことをおすすめします。
分割納付している場合も、残りの期分がいつまでか把握しておきましょう。
日割り精算の特約があるか契約書をチェック
最後に、もう一度強調しておきたいポイントです。
日割り精算は慣習であり、法律上の義務ではありません。
そのため、売買契約書に「公租公課は日割り精算する」という条項がなければ、精算されないこともあります。
ごくまれに、特約で「固定資産税等の精算は行わない」とされているケースもあります。
この場合、売主は1年分の固定資産税を全額負担することになり、買主から精算金を受け取ることができません。
契約書を受け取ったら、必ず固定資産税の精算に関する条項を確認してください。
わからない場合は、遠慮なく不動産会社の担当者に質問しましょう。
よくある質問
Q. 固定資産税の精算金は売買代金に含まれますか?
A. 固定資産税等の精算金は、売買代金とは別に授受されます。
精算金は、決済時に売買代金と一緒に支払われることが多いため、混同しやすいのですが、売買代金とは別のものとして扱われます。
これは税務上も重要で、精算金は売買代金ではなく「固定資産税の一部を買主が負担した」という性質のものです。
不動産売却の確定申告をする際も、精算金は譲渡価額には含めません。
売買契約書や領収書でも、売買代金と精算金は分けて記載されます。
Q. 固定資産税が口座引き落としになっている場合はどうすればよいですか?
A. 売却前に口座引き落としを解除する手続きを速やかに行うか、全額納付してから精算するのが安全です。
固定資産税を口座引き落とし(自動振替)にしている場合、売却後も引き落としが続いてしまう可能性があります。
売却が決まったら、自治体に連絡して口座引き落としを解除しましょう。
まとめ
不動産売却時の固定資産税について、重要なポイントをまとめます。
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人です。
そのため、年の途中で売却しても、法律上は売主が1年分を納める義務があります。
しかし、実務では引渡し日を基準に日割り精算するのが一般的な慣習です。
買主が所有する期間分の税金を、決済時に精算金として受け取ることができます。
日割り計算では、精算の起算日が地域によって異なることに注意が必要です。
関東圏では1月1日起算、関西圏では4月1日起算が多いです。
売買契約書には必ず起算日を明記し、売主・買主双方で合意しておきましょう。
また、トラブルを避けるために、
- 起算日を契約書に明記する
- 税額確定前は前年度の金額で暫定精算する
- 売却前に未納がないか確認する
- 日割り精算の条項が契約書にあるかチェックする
これらの点を必ず確認してください。
不動産売却は、多くの方にとって人生で何度も経験することではありません。
だからこそ、固定資産税のような細かい部分まで理解しておくことが、安心して取引を進めるために大切です。
当社は、宅地建物取引士とファイナンシャルプランナーの資格を持つスタッフが直接対応し、売主様の疑問や不安に丁寧にお答えしています。
不動産売却に関して、わからないことや不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。
▼無料相談のお申し込みはこちらから
不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。