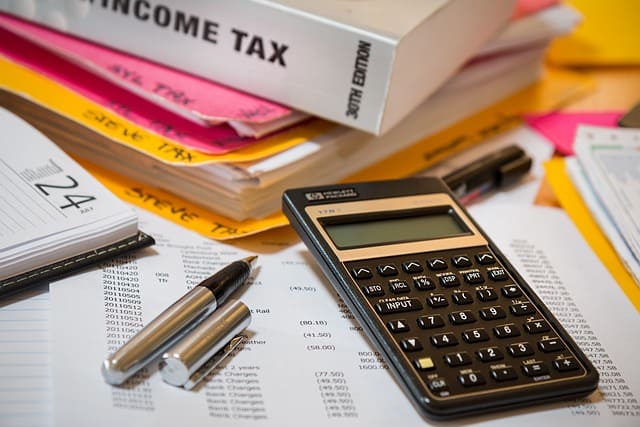blog
土地売買のトラブル事例|安心取引への近道

- Blog
「土地を購入したいけど、何かトラブルに巻き込まれないか不安…」 「売却する土地で思わぬ問題が発生したらどうしよう…」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
実際、土地売買では表面上わからない「隠れたリスク」が多く存在します。
これらのリスクを知らずに取引を進めると、後から大きなトラブルに発展することも。
今回はそんな「土地売買における様々なトラブル事例」と、安心して取引を進めるためのポイントをご紹介します。
目次
土地売買でトラブルが発生する主な原因
土地売買のトラブルは、多くの場合「知らなかった」「確認していなかった」ことから生じます。
土地は一般的な商品と違い、一つひとつが個性的で、様々な権利関係や法的制限が絡み合っています。
また、地中の状態や周辺環境など、目に見えない部分に問題が潜んでいることも少なくありません。
こうした特性から、売主・買主双方の認識の違いや情報の非対称性によってトラブルが発生しやすくなっています。
事前の確認や専門家によるサポートが特に重要となる理由はここにあります。
境界問題で揉めないために!境界確定と越境の事前確認
土地売買でもっとも頻繁に起こるトラブルの一つが境界問題です。
境界未確定による紛争リスク
土地の境界が明確に確定していないと、隣地所有者との間でトラブルに発展することがあります。
「自分の土地だと思っていた部分が実は隣の土地だった」というケースは珍しくありません。
このような「筆界未定」の状態で建物を建てたり、フェンスを設置したりすると、後から移設や撤去を求められるリスクがあります。
境界の確定を行い、隣接地所有者の立会いのもとで境界を確認しておくことが重要です。
越境物の有無の確認
隣地から樹木や建物の一部が越境していたり、逆に自分の土地から隣地へ越境していたりする場合もあります。
こうした「越境物」は、将来的に撤去を求められるリスクがあります。
特に古い住宅地では、長年の間に少しずつ境界線があいまいになり、知らず知らずのうちに越境状態になっていることもあります。
売買前に現地を詳細に確認し、越境物の有無を把握しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
思わぬ出費の原因に?地中埋設物のリスクと対策
目に見えない地下には、様々な問題が潜んでいることがあります。
過去に建物があった土地では、解体時に地中に基礎の一部や杭が残されていることがあります。
また、産業廃棄物が不法に埋められているケースも。
このような地中埋設物は、新たに建物を建てる際に追加工事や撤去費用が発生する原因となります。
最悪の場合、計画変更や多額の追加費用が必要になることもあります。
地中の状態を完全に把握することは難しいですが、事前調査と契約書での取り決めにより、リスクを軽減することが可能です。
建築できない土地に注意!接道義務と再建築不可物件
土地を購入する最大の目的は、多くの場合「建物を建てること」ではないでしょうか。
しかし、すべての土地に自由に建物が建てられるわけではありません。
接道義務とは
建築基準法では、建物を建てるためには原則として幅員4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接していることが必要です。これを「接道義務」と呼びます。(建築基準法第43条に基づく)
この条件を満たさない土地は、建物の建築や建て替えができない「再建築不可物件」となってしまう可能性があります。
接道義務を満たしているかどうかは、市区町村の建築指導課などで確認できます。
セットバックが必要なケース
幅員4m未満の道路に接している場合、「セットバック」と呼ばれる後退距離を確保する必要があります。
これは道路中心線から2mの位置まで敷地を提供する義務のことです。(建築基準法第42条第2項に基づく)
セットバックが必要な場合、その分だけ有効な敷地面積が減少するため、建築計画に影響を与えることがあります。
土地購入前に、接道状況とセットバックの有無を確認し、実際に建築可能な有効敷地面積を把握しておくことが大切です。
土地購入前に確認したい!埋蔵文化財包蔵地の制限と対応策
意外と見落とされがちなのが、埋蔵文化財に関する制限です。
埋蔵文化財包蔵地の意味と影響
埋蔵文化財包蔵地とは、地下に埋蔵文化財(遺跡や遺物)が存在する可能性がある区域のことです。
このような区域では、建物の建築や開発を行う際に事前の届出や調査が必要になることがあります。
調査の結果、重要な遺跡が発見された場合は、工事の中断や計画変更を求められることもあります。
これにより、予定外の費用や工期の延長が生じる可能性があります。
事前の確認方法
対象となる土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、各自治体の担当部署で確認できます。
また、一部の地域では、インターネット上で埋蔵文化財包蔵地マップを公開しているケースもあります。
土地の購入を検討する際は、埋蔵文化財に関する制限についても事前に調査しておくことが賢明です。
契約不適合責任とは?トラブル防止のための契約書作成のポイント
2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」に代わって「契約不適合責任」という概念が導入されました。(2020年4月1日施行の改正民法に基づく)
契約不適合責任の範囲
契約不適合責任とは、引き渡された土地や建物が契約の内容に適合していない場合に、売主が負う責任のことです。
具体的には、修補請求や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの対象となります。(民法第562条〜564条に基づく)
売主が個人の場合でも、地中埋設物や土壌汚染など、「隠れた瑕疵」について責任を問われる可能性があります。
トラブル防止のためには、契約書に責任の範囲や期間を明確に定めておくことが重要です。
特約条項の活用
売買契約書には、契約不適合責任の範囲や期間、免責事項などを特約条項として明記することができます。
これにより、売主・買主双方の認識を一致させ、後々のトラブルを防ぐことができます。
例えば、「引渡し後〇カ月以内に発見された契約不適合について責任を負う」などの条項を設けることが可能です。
特約条項の内容によっては買主に不利になる場合もあるため、公平な契約内容を検討することが大切です。
「言った・言わない」を防ぐ!引渡し条件の明確化と現地確認の重要性
土地の引渡し条件をめぐるトラブルも少なくありません。
引渡し条件の認識違い
買主は「更地での引渡し」を期待していたのに、売主は「現状有姿(現在の状態のまま)での引渡し」を想定していた——このような認識の違いから、引渡し時にトラブルになるケースがあります。
特に、古い建物や樹木、残置物の撤去に関する認識の違いは、多額の費用負担の問題に発展することがあります。
現地確認と引渡し内容の文書化
引渡し条件についての認識違いを防ぐためには、口頭での確認だけでなく、具体的な内容を契約前に引渡し条件(更地・現状有姿・一部撤去など)を明確にし、契約書に明記しておくことが重要です。
特に「何を撤去するか」「どの状態で引き渡すか」双方の認識を一致させることで、引渡し時の「聞いていない」「言った・言わない」というトラブルを未然に防ぐことができます。
必要に応じて写真記録を残しておくと安心です。
私道に関する権利関係と事前調査の必要性
私道に接する土地の場合、特有の問題が生じることがあります。
私道の通行権と負担
対象となる土地が私道に接している場合、その私道の所有権や通行権が確保されているかが重要な問題となります。
また、私道の維持管理費用や修繕費用の負担についても確認が必要です。
私道の所有者や権利関係を確認し、将来的なトラブルを防ぐことが大切です。
上下水道等の引き込み工事の承諾
私道を経由して水道・下水道・ガスなどを引き込む場合、私道の所有者や共有者全員の承諾が必要とされることがあります。
こうした承諾が得られないと、ライフラインの整備ができず、建物の建築や居住に支障をきたすことになります。
土地購入前に、私道の権利関係や掘削承諾の取得可能性について調査しておくことをおすすめします。
まとめ:安心して土地売買を進めるために
土地売買におけるトラブルを防ぐためには、事前の調査と確認が何よりも重要です。
- 境界をはっきりさせる
- 越境物の有無を現地で確認する
- 地中埋設物のリスクを調査し、契約書に取り扱いを明記する
- 接道義務を満たしているか、セットバックの必要性を確認する
- 埋蔵文化財包蔵地に該当するか調査する
- 契約不適合責任の範囲と期間を契約書に明記する
- 引渡し条件(更地・現状有姿など)を明確にする
- 私道の権利関係や掘削承諾の必要性を確認する
ここでご紹介したのはあくまでも土地売買におけるトラブルの一例です。
実際には、物件ごとに固有の事情や地域特有の問題が潜んでいることもあります。
これらすべてを自分で調査・確認するのは非常に労力がかかり、専門知識も必要です。
そのため、土地売買を検討される際は、まずは不動産会社に相談してみましょう。
長崎県大村市を拠点に地域密着で活動する株式会社あこう不動産は、お客様一人ひとりに寄り添った丁寧な対応を心がけています。
まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。
▼無料相談のお申し込みはこちらから
[不動産について相談する]
[無料査定を依頼する]
[LINEで相談する]
不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。